子どもを英語教室に通わせていて「なぜ、もっと英語の文法を教えてくれないのかしら」と不満に思ったことはありますか? お母さんが中学校のときは文法中心に英語を学び、テストでも問われたのは文法理解が中心でした。
まだまだ時間はあるとはいえ、将来の受験のことを考えると「文法を教えて欲しい」と思う気持ちもわからなくはありません。
小学生に文法を教えない理由のひとつは、文法を教えるには小学4年生までは幼過ぎるからです。文法学習とは抽象的な概念を理解することです。一般的に小学5年生以上でないと、文法学習はうまくいきません。
もうひとつの理由は、子どもが通っている英語教室でも実は「文法をきちんと教えている」のかもしれません。でも、お母さんが中学校で習った方法とは異なるので、文法を教えているように感じないだけです。
小学5年生くらいからは少しずつ文法を教えられます。ただし、小学生に教えるときにはコツがあります。これは英語教師の仕事の範疇です。でも、お母さんが大まかにそのコツを理解しておくことはとても有意義です。
Contents
小学生に英語の文法を教えるときは、帰納法が基本
お母さんが中学校や高校のときに受けた英語の授業を思い出してください。おおまかにいえば「最初に文法の説明→練習問題・読解→答え合わせ」の順番だったはずです。このような授業展開は「演繹法(えんえきほう)」と呼ばれています。
演繹法で、小学生に英語文法を教えても「英語嫌い」を量産するだけです。ここでは「小学生に適した英語文法の指導法」について詳しく説明します。
帰納法と演繹法
初めに「帰納法(きのうほう)」と「演繹法(えんえきほう)」について説明します。この際厳密な定義は無視して、車の運転に例えることにします。
「帰納法」で車の運転を覚える場合、実際に運転をするところから始めます。エンジンをかけてドライブにシフトすると車はスルスルと動き始めます。慌てた初心者ドライバーはブレーキと思い、右側のペダルを踏むと急発進。正面の壁にぶつかって止まります。
ここでドライバーは、ドライブに入れるとスルスルと動くこと(クリープ現象)と右側のペダルがどうやらアクセルであることを理解します。このようにして、実践を重ねながら車の仕組みや交通ルールを覚えていくのが「帰納法」です。
「演繹法」では、最初に車の仕組みと交通ルールをきっちりと教わります。そのあと実際に車に乗って、覚えた知識に従って車の運転をします。これが「演繹法」です。
車の運転は命にかかわります。だから教習所では、演繹法と帰納法のバランスをうまくとりながら教習が進められます。でも、小学生が英語文法を学ぶときは、「帰納法」で教えたほうが圧倒的に理解は早いです。
英語で何度間違えても、命の危険はありません。では、英語文法の学習における実技教習に相当するものとはいったい何でしょうか?
音読を繰り返すと、自然と法則を見出してボンヤリと理解し始める
小学生にとって英語の音読練習は「教習所内の技能教習」です。いきなり「英語を話しましょう」といわれてもポカンとして何をすればいいのかわかりません。
そこで、シンプルで正しい英語をいくつも与えて大きな声で音読させます。このとき、意味もわからずお経のように唱えていても効果はありません。きちんと意味を理解している状態で、何度も音読させます。
このような訓練を繰り返すと、子どもなりにボンヤリと英文の「法則」や「ルール」を理解し始めます。
音読から文法を学ぶ例
ピコ太郎さんの「PPAP」は一時期大流行しました。おそらく小学生も何十回と知らず知らずのうちに「I have a pen.」と歌いながら「英語を音読」したはずです。
映像から「私はペンを持っている」という意味は明らかです。それを何度も口頭練習します。そのうち勘のいい小学生は、英語では「私は/持っている/ペンを(主語+動詞+目的語)」の順番になることを覚えてしまいます。
ここまで口頭練習を積み上げた段階で、お母さんや先生が英語の基本的な語順について少しだけ説明してあげれば、小学生でも無理なく文法を理解できます。これが帰納法のメリットです。
初めに口頭練習したあとに、文法をあたえよう
このように小学生に英語文法を教えるときは、初めに口頭練習をたっぷり与えてから、最後に「ざっくりとした」文法を教えます。これが最も効果的な指導法です。
英語が得意なお母さんはつい、初めに文法を教えてからワークブックに取り組ませようとします。これはお母さんがかつて受けた演繹法による授業の影響です。
実はプロの英語教師もついやってしまいがちな失敗です。自分が受けてきた英語教育の呪縛からなかなか抜け出せず、同じ指導を繰り返してしまうのです。
長年、子どもに英語を指導してきた先生を観察していると、この「帰納法」の原則を忠実に守っています。
細かいところにどこまで目をつぶるか
ではなぜ、中学や高校では帰納法による英語文法の指導が主流でないのかという疑問が残ります。それは、多くの情報を伝えるときは「帰納法」は効率が悪すぎるからです。
たとえば名詞に複数形のsをつけるときに、演繹法ならこのように指導できます。
- sだけ最後につける
- 語尾がs, x, sh, ch, oのときはesをつける
- 語尾がf, feのときは、f, feをvに変えてesをつける
- 子音字+yで終わるときは、yをiにかえてesをつける
このあと問題に取り組みながら、複数形の作り方を覚えていきます。
帰納法で教える場合、“I don’t have a watch, but my dad has a lot of watches.”のような文に繰り返し触れることにより、何となく「watchはwatchesだったような…」という感覚を覚えるところまで進めます。そして最後に、先ほどのルール2を与えます。
一つひとつのルールにたいして大量の文を与えて音読をするとなると、膨大な時間を必要とします。これが、中学高校の授業ではあまり採用されない最大の理由です。
「効率的に英語文法を学べるなら小学生にも演繹法で教えるべきでは?」と思うかもしれません。でも、それは実際には難しいのです。なぜなら多くの文法事項を初めに教えると、小学生では英語嫌いになったり、そもそも理解できなかったりするからです。
今の段階で何を優先させるかを見極める
小学生には帰納法中心の指導が優れているのは間違いありません。なぜなら、細かい文法の知識は不要だからです。教えるべき大切な部分にだけ絞り、帰納法で扱うのが良いのです。
正しくない英語でも、「目をつぶれる部分と目をつぶれない部分」があります。この見極めができるのがプロ教師の腕の見せどころです。
「目をつぶれる間違い」とは、たとえば“I have a lot of watchs.”(正しくはwatches)のような間違いです。「目をつぶれない」のは、“I a lot of watches have.”のような語順に関する間違いです。
文法は「英語理解のためにどうしても必要な部分」に絞り、帰納法で教えていくのが大切なポイントです。
小学生での英語の文法は、彫刻でいえば「面取り」の段階で充分です。
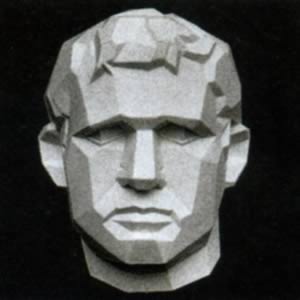
これを中学・高校の英語の授業で細かいところを整えていき完成させるイメージです。

初めから細部にこだわり過ぎる文法指導は小学生には禁物です。
やっかいな三単現
「三単現(三人称・単数・現在形)のs」は教えるのが難しい項目のひとつです。私だったらまず、簡単な英語の本を音読しながら動詞にsがついた文とsがつかない文を大量に音読させます。
しばらくすると、子どもは「あれ?」と気がつきます。「動詞の部分にsがつくことがあるけれど、なぜだろう?」と不思議に思うのです。
自分から質問してきたときが、最初に教えるタイミングです。
何となく理解している子ども
ネイティブの子どもでも、三単現のsは「何となく使い分け」している状態です。きちんと根拠を説明できるわけではありません。
インター校の教室に掲示されていた作文を読むと、Year 3(日本の小2くらい)のネイティブの生徒でも、s を書き落としているミスを見つけたことがありました。
おそらく彼らの頭の中では「過去形にはsはつけない。いつものことを説明するときに、その場にいない人でひとりのときはsをつける。ひとつのものにもつける」程度の理解です。
小学生ならこれで充分ですし、まったく間違っていません。
私の失敗談
インター校に通っていた息子が小学2年生のころでした。宿題で書いた作文に先生が三単現のsを赤ペンで書き足していました。息子はこのとき初めて「なんでこうなるの?」と質問してきました。
これ以前に、すでに“Does he ~?”とか“He doesn’t ~.”などの表現は話していたので、理解していると私は思っていました。
そこで試しに中学生に教えるように、理屈をこねて説明してみました。するとすぐに大きなあくびをし始めて飽きてしまいました。完全にやってはいけない指導法です。
今の私なら次のように指導します。
S: I have some books.
T: Ok. How about your sister?
S: She has some books, too.
T: Why did you say “has” instead of “have”?TはTeacher(先生)、SはStudent(生徒)
このように導けば、どういう場合に動詞にsをつけるのかをぼんやりと理解しはじめます。こうして、何回か口頭練習したあと、最後にまとめとして簡単な文法の説明をします。
もちろん、すぐにスッキリとは理解できません。何度も何度も間違えを繰り返して、ようやく少しずつ理解します。根気よく待つしかありません。ちなみに息子が「三単現のs」をほぼ間違えなくなったのは、小学4年生になってからでした。
口頭練習による対比が理解のポイント
子どもの指導に有効な帰納法を用いる場合は「対比させる」のがポイントです。このことを理解するために、「現在完了形」を例に挙げて説明します。
- 現在完了形を例に
S: My birthday is May 5th, 2010.
T: Where were you born?
S: I was born in this town.
T: You lived in this town 10 years ago, right? (黒板に書く)Where do you live now?
S: I live in this town.(黒板に書く)
T: Oh, you have lived in this town for 10 years! (黒板に書く)TはTeacher(先生)、SはStudent(生徒)
10years ago
I lived in this town 10 years ago.
now
I live in this town.
→I have lived in this town for 10 years.
10年前についての情報を過去形で、現在の情報を現在形で表現して対比させます。そして、現在形の一種として「(今では)10年間ずっとこの町に住んでいます」という現在完了形の感覚を覚えさせます。
帰納法で学ばせるときは、いかに効果的な対比を見せられるかがポイントです。
このようにしてできた自分に関する現在完了の例文を何度も口頭練習させます。すると、最初のhaveは「持つ」という意味はなく、「ずっと~してきた」の意味を添えたいときに使っているだけだと何となく理解し始めます。
もちろん、最後はかならずまとめとして情報を整理してあげます。すると子どもは「ああ、やっぱりな」と腑に落ちます。もし、自分の理解に誤りがあればここで気づくので、それはそれでいい勉強になります。
すべて理解したところで、ダメ押しの口頭練習が必要です。忘れた頃に反復して練習します。このようにして、少しずつ英語の力をつけていきます。
ガチガチの文法用語から入ると、英語の心は理解できない
もし、先ほどの「現在完了形」を演繹法で、文法用語から導入したらどうなるでしょうか? 優秀な小学5年生なら、中学生と同じく理解してしまう子どももいるかもしれません。でもそれは「理解」であり、「使える」文法にはなりません。
「現在完了形: have (has) +過去分詞形=ずっと~してきた(継続)」を最初に学んでも、空欄補充のテスト以外で役に立つことはありません。
“I have lived in this town for 10 years.”と話すときの話し手は「僕はこの町に10年住んでるよ(だから、(今)僕は君よりこの町について詳しいよ)」という心情が現れています。
この感覚をつかむためには、実例に即して口頭練習を積んでから文法を理解しないといけません。
テストで正解をもらうだけなら知識だけでもなんとかなります。しかし、「本物の英語力」を身につけるためには「なぜ、その表現(文法)は必要なのか?」まで深く理解しないと、使えるようにはなりません。
この観点でみると、haveに続く過去分詞形を少々間違えたとしても、たいした問題ではありません。
このように自分の体験に関連した英語を対比させて、口頭練習を充分に積んだ後に情報を整理してあげるのが小学生には効果的な文法の教え方です。
小学生の間に口頭練習を積むのが大切
小学生の間に口頭練習を大量に積んでおくと、中学校での英語の授業をとても有効な時間にできます。学校英語では英語を話せるようにならないと批判されますが、活用しだいではありがたい文法確認の貴重なチャンスなのです。
先ほどの現在完了形で、過去分詞形の理解が曖昧だったとします。それでも口頭練習をたくさんすると、have made, have read, have watched…のように口と耳が何となく覚えています。
もちろん、間違えて覚えているところもたくさんあります。その部分をきっちりとあぶりだして、仕上げていくのが学校での英語の授業です。すでに英語の心がわかり、使うシチュエーションを理解し、発音をできる状態なので、最後に知識を固めれば鬼に金棒です。
中学校の英語の授業をゼロから学んでも、話せるようになるまでに長時間必要です。でも、小学生までに口頭練習を積み上げていれば、英語を話せるようになるまであと一歩です。学校英語はムダではないのです。
こちらの動画セミナーでは音読トレーニングを通じて、英語4技能の向上を図る方法を紹介しています
考える割合が減る(=無意識化)は英会話への第一歩
すでに音読練習をしていて仕上げの文法を覚えれば、それほど考えなくても口をついて英語表現が出てくるようになります。ほんの一瞬頭を使うだけで文章の構文を思いつくので、難しい部分やうまく伝えるための論理展開に頭を使えます。
英語を話せる人達は、頭を使わずに英語を出せる(話す・書く)割合が多いのです。これが英会話のコツです。小学生のうちに音読訓練をしておくと、中学高校で英語力のカーブは急上昇します。
中学・高校で一気に英語力を伸ばすために
小学生の段階で、「英検〇級」というテストの結果にこだわり過ぎると、お母さんはあせって結果を求めようとしてしまいます。
音読練習をすると確実に英語力は向上しますが、必ずしもテストの点数に反映されません。テストでは「〇か×」を問われます。「70%の理解」は「×」だからです。帰納法による文法学習はテストの点にすぐには反映されません。
子どもは楽しく努力をしてせっかく英語力を蓄積しているのに、低く評価されたり怒られたりしたらたまったものではありません。中学高校にすすんで、授業で文法の完成度を上げればテストの点などあとからついてきます。
帰納法中心で学ぶ子どもに対しては、テストの点に現れない部分をお母さんに評価して欲しいと思います。そうすれば子どもも「お母さん、わかってくれているな」という感覚を持てるはずです。
まとめ
子どもの英語学習の8割は音読練習に充てられるべきです。音読練習とは、教科書を声に出して読むだけではありません。お母さんの口まねをして英語を話すのも立派な音読練習です。英語の歌を口ずさむのも音読練習のひとつです。
子どもは大量の英語に触れながら、少しずつ英語の語順などを自然と身につけていきます。このような「あいまいな理解」をしたところで、少しずつ文法の説明を受けて理解を確かな物にしていきます。
試行錯誤を繰り返しながら規則性をボンヤリと見つけさせ、最後に教師がまとめで知識を与える「帰納法」が子どもへの文法指導には有効です。
小学生までに音読練習を積み上げておくと、中高での英語の授業はあいまいな知識をチェックする時間になります。それまでの疑問点は一気に晴れますし、迷いがなくなるので「使える英語」を身につけられます。
小学生の頃に文法の知識ばかりを詰め込んでも、英語を話せるようにはなりません。上手な英語の先生なら、口頭練習を多くとりながら文法のまとめをしています。
小学生に英語の文法を教えるときは、いろいろと気をつけなければいけません。安心して英語教室に通わせるためにもこのことを理解しておくと良いです。
